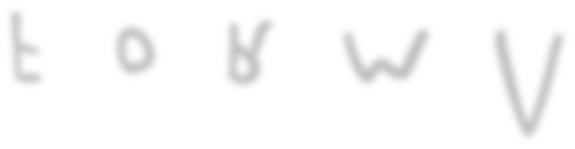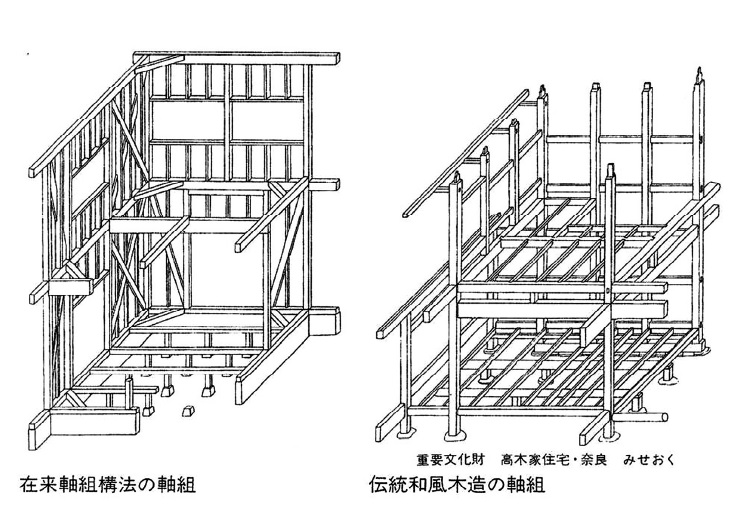category
-2019.2.9-
音楽室・防音室とリビングが自然につながる方法は?
こんにちは。京都の設計事務所FORMAフォルマの中西義照です。
先月、お正月早々に京都市西京区桂坂にある、音楽室のある家#02 の撮影に伺いました。毎年恒例で冬休みにお友達が集まるそうですが、お友達と一緒のセッション大会がとても楽しそうでした。
音楽室内には、マリンバ、ピアノ、ギター、打楽器など演奏者が5人。リビングのお友達も演奏しているように楽しそうです。
リビング側に大きな窓をとり、リビングと音楽室に一体感があるからこそできる楽しみ方だと思います。
こちらの音楽室のある家#02 の特徴は、マリンバが入る音楽室が家の中心にあることです。暮らしの機能は音楽室の周囲に配置されています。リビングとつながる音楽室について今回は床の高さについて説明します。
音楽室とリビングが同じ床の高さの場合
・マリンバの高さは80~90cmほどあります。窓側にマリンバが配置された場合、窓の高さの半分を占めることになります。リビングにいる人はかなり圧迫感を覚えそうです。(リビングと音楽室の広さにも関係します。)
・マリンバは立って演奏するので奏者の視線は高くなります。演奏する手元とリビングに座る人の目線の高さが同じくらいになります。手元は見やすいかもしれませんが、リビングとつながる音楽室の楽しさを考えると、音楽室とリビングにいる人の目線の高さは近い方がより楽しさを感じると思います。
音楽室の床の高さを下げた場合
・存在感のあるマリンバは、奏者の手元あたりだけが見えるほうがリビング側の圧迫感が少なくなる。
・奏者の視線と、リビングに座る人の視線の高さが近くなる。
・音楽室の床をリビングの床と切り離すことで振動への防音性が高まる。
・奏者からも庭が見え空も見えると尚良い。演奏時の気持ちよさにつながる。
・音楽室の床を下げることで2階の床が低くなりリビングと2階との距離が縮まり空間の一体感が高まる。
音楽室に窓をとることだけではない、音楽室とリビングが自然につながる方法です。
さらに、こちらの住まいの特徴である家の中心に音楽室があるという間取について、音楽室が外壁に面していないということは、外部への防音効果をより高めることにつながっています。
住まい手のKさんからは、リビングから見えるマリンバに圧迫感を覚えることなく音楽室がすっきり見える。演奏していてもリビングで座っていてもどちらも関係性が気持ちがいいと、暮らして使った感想をお聞きしました。
音楽室といえば防音が重要になることはもちろんですが、暮らしとの関係性のバランスを整えることで、演奏している人も普段の暮らしがある場所も、どちらも心地よいにつながるいい塩梅のところを探りながら作っていくことが大切だと思います。
床の高さに変化をつけることは、音楽室とリビングが自然につながる方法の1つです。楽器による違いもあり、まだまだ気持ちの良い高さを探りたいところです。
音楽室・防音室の事例は、どうぞこちらから「音楽室のある家」ご覧ください。
お気軽にご相談下さい。