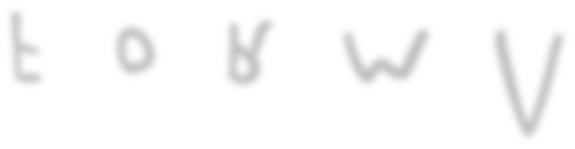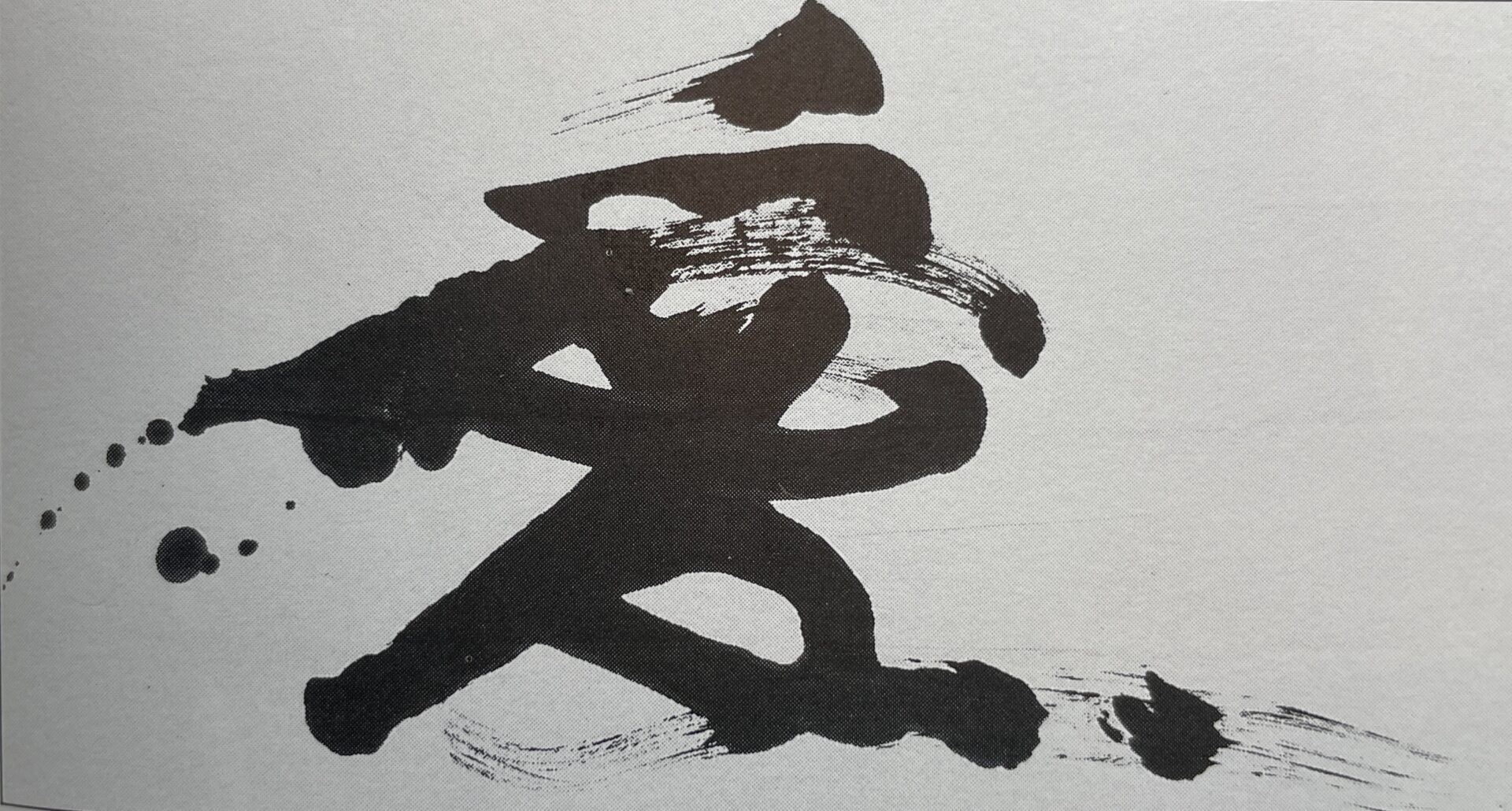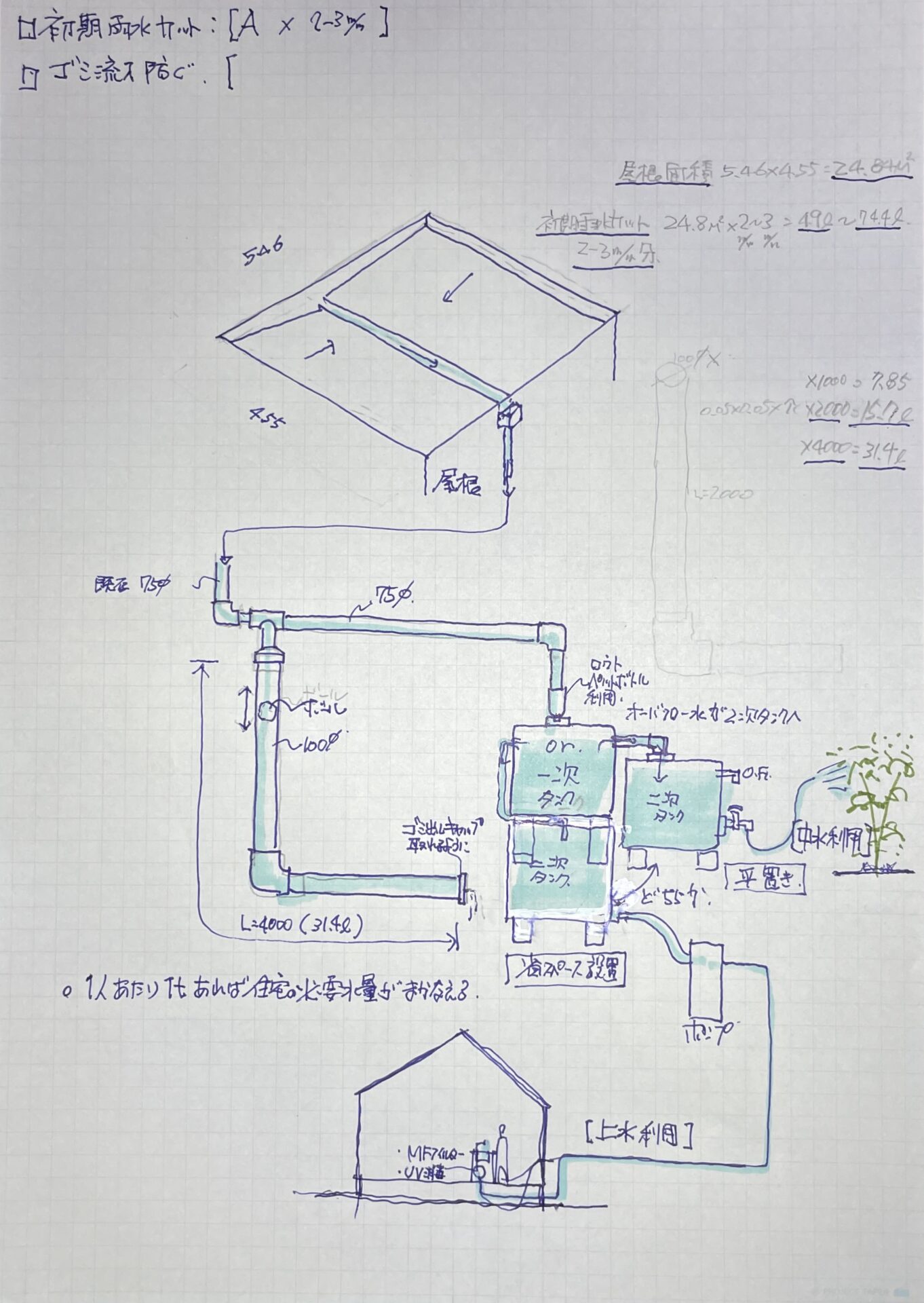category
-2025.5.1-
氣を読む建築 第三回【 柔と剛:構造と余白の間にあるもの】
|境界を、しならせるということ
この世界は、線引きによって理解されます。
内と外、私とあなた、強さと弱さ、動と静。
けれど、合氣道を稽古していると、次第に気づいてきます。
本当に力が発揮されるのは、「その境界がゆらいだ瞬間」だということに。
たとえば、相手の力を受け流すとき、身体は一度しなり、一つになる事。
あえて抗わず、流れに身をゆだねる。
そして最小の動きで、最大の調和を生み出す──
「柔よく剛を制す」とは、境界をコントロールする技でもあります。
建築もまた、境界の芸術です。
とくに「内と外のはざま」=中間領域において、
剛と柔、かっちりとふわっとは交差し、どちらともつかない新たな場が立ち上がります。
|はざまの力──“つなぐ”ことで生まれる氣
内とはどこからどこまでなのか。
外とは、どこから“外”になるのか。
建築では、これを明確に定義することもできます。
ドア、壁、窓、屋根──それらは空間を「囲い」、世界を切り分けます。
しかし、人が心地よさを感じるのは、案外、
その「境い目」や「グラデーション」の中であることが多いのです。
◎軒下、縁側という“あいまいな場”
家の中でも外でもない。
けれどどちらの氣配もある。
虫の声、風のにおい、地面の温度を感じながら、
同時に天井や柱の安心感にも包まれている。
この軒下、縁側は、「剛」=構造的な囲いをもちながら、
「柔」=自然との連続性を保つ空間です。
◎中間領域の設計──かっちりと、ふわっとの交差点
- 壁に設けた大きな開口部から、光と風がふわっと入る
- 格子戸が視線を通しながらも、存在感を保つ
- 天井の高さを変えることで、場の緊張と緩和が生まれる
- 植栽が内の場に静かに侵入してくる
こうした中間にある事象の操作は、空間の「氣」を調律する行為です。
剛が全体を支え、柔が氣を巡らせる。
その両者の“はざま”に、人は居場所を感じ、
建築に対して「共にある、繋がっている」という感覚、意識を持つのかもしれません。

|型の中で、境界はどう変化するか?
合氣道の型もまた、決まった「形」をなぞることで学びます。
しかし、実際に相対したとき、動きは固定されません。
状況に応じて、変化し、応答し、しなる。
建築においても、設計という「型」をつくった瞬間から、
その空間は外部と接し、関係し、揺らぎ始めます。
最初の意図とは別の使われ方をされることもあるでしょう。
想定外に拡張された使い方それこそが、「かっちりと、ふわっとの間」に宿る智慧です。
建築が生きている証、拡張性はそこに宿る人の営みの原理として考える事が出来ます。
|中間領域が育てる“氣の流れ”
私たちはつい、何かをはっきり分けたくなります。
けれど、合氣道も建築も、本質は「間」にあります。
剛に偏りすぎると、空間は硬直し、
柔に傾きすぎると、意味を失う。
だからこそ、そのあわいを設計することが、
本当に氣の通った建築を生み出す鍵なのです。
かっちりと構成、設計された構造(ストラクチャー)があり、
ふわっと風や意識が抜ける中間領域(インターミディエイト・スペース)がある。
その“間”に、人の暮らしが育ち、
建築がただの器ではなく、「氣をもつ場」となる事を目指します。
次回予告|
第4回は氣の通り道、重力と氣の流れを読む:空間に流動性を
風が抜け、光が巡り、音が響く。
家が静かに呼吸するような空間には、見えない設計の力が宿ります。
次回は「氣の流れ」を形にする方法について考察します。
一級建築士事務所FORMA
中西 義照
建築や空間、道場をつくる構想がありFORMAの考え方をもう少し詳しく聞いてみたいという方は
SNS【FB/インスタグラム/X/LINE】でつながっている方は直接メッセージでお知らせください。
又は、このホームページのお問い合わせからお願いしたします。