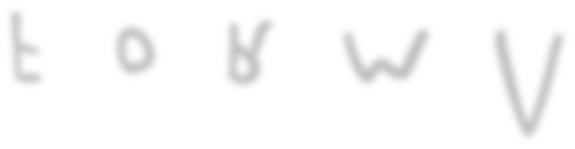-2025.5.25-
みちくさの森で皮むき間伐をしました!
5月18日(日)みちくさの森(ミライマから徒歩15分の森)で、旧青野小学校区で地域づくりに取り組む「青のたすき」さんと、「ミライマ」がタッグを組んでの初めての皮むき間伐を行いました。
今回の講師は、山守のにしけんさんこと西本賢さん。参加者は、大人12名、子ども4名。
間伐の方法がわかったり、皮むきができただけではなく、森を楽しむ子どもたちの姿や、参加されたみなさん一人一人の森の感じ方、盛り上がった懇親会まで、いろいろな場面に心が動きました。
ー皮むき間伐とは?ー
木は根っこから養分を吸収して幹が太りますが、樹皮をはいでしまうと、水分や養分を吸い上げることができなくなります。皮むきをされた樹木は、葉っぱや枝が枯れ落ち木は立ち枯れになるので、自然に乾燥して軽くなり、伐採や搬出、作業が楽になります。

前日、にしけんさん、青のたすきのりえさん、テルさん、私の4人で準備を兼ねて下見に行きました。
みちくさの森は、杉の森、檜の森、雑木の森があるようで(私は初めて行きました)、間伐は植林した杉や檜の森で行います。
今回、開催場所に選んだ檜の森は、杉の森のような地面にモサモサした落ち葉がなく、歩きやすく気持ちがよいのです。川沿いを覗くと大雨のせいでしょうか、木が根っこから倒れていて、おかげでそこの視界が開け下草も生えていました。

崩れ落ちた根っこについた土から、杉や檜の新芽がニョキニョキ。この可愛さといったら。すっかり皮むき間伐の下見だということを忘れてしまいそうでした。

一緒に行った講師のにしけんさんも、青のたすきの理恵さんも、みんな森の魅力にひき込まれています。この感覚の共有、なんともうれしく楽しかったです。

さて、当日は雨も降らず、ちょうどいい気候に恵まれました。講師のにしけんさんから皮むき間伐についての説明と、森の所有者であるテルさんからは、間伐した後の森の妄想スケッチを見せてもらいました。

みんなで皮をむく前に、竹べらを使って皮を剥ぎます。この下準備も子どもたちの力でできますが、子どもたちはすぐに川に楽しいことを見つけたようで、あっという間に姿が見えなくなりました(笑)

最初の1本!みんなで檜の皮を持って声を合わせて引っ張ります。
ベリベリ〜
歓声が上がります。皮むきした檜の表面のきれいさは写真からも伝わると思いますが、触るとみずみずしくツヤツヤです。
実際には、皮むき前に、10m×10mの範囲にある木の太さを測り断面積を計算し、そこから適正な基準値に持っていくのにどの木を間伐するのかを決め、それから皮をむきます。



お昼は弄月庵でブッダボウルのランチです。これがまた美味しいのですよ。みんな会話が弾みます。

午後からいよいよ本番で、合計11本の檜の皮むきができました。

ラストは、大人も子どもも今日の感想をシェアして、にしけんさんの三味線に合わせて、森への感謝を込めて歌います。楽しいだけではなく、森へ思いを寄せることができるひととき。

皮むき間伐をする目的や意味は人それぞれの考え方や立場によるだろうと思いますが、自分なりに振り返ると体験したからこその気づきがありました。
ー密になりすぎた森をゆるやかに間引き整えること。それは自分を整える作業と通じる。ー
まず、そこが密になっているという認識があって、それは何かしらこのままいくとよくないとわかっていたり、すでによくないことが起こっていたり。その環境をよくみて感じることからはじまり、間引きの対象になる木を見つける。
その見つけ方の一つは、「ここがどうなるといいだろうを想像する」こと。
対象になる木とコミュニケーションをとりながら、誰でもができる方法で、1人ではなく人と一緒に皮をむく。そうすると、この後、徐々に葉っぱが枯れていき、そこから光が少しずつ入り、大地にゆるやかな変化が生まれていきます。
やってすぐに結果がでるわけではないですが、少しずつ、でも確実に、そこに何かしらいい変化がおこることを、少し時間軸を長くして見守る。
森を整えることと自分を整えることが、自分の中で通じたのでしょうね。個人的な感想です。

今回参加してくださったみなさんは、みちくさの森の最初の姿を知ってくださった人たちになります。1年後、2年後、5年後、10年後、この森の変化を楽しく見守っていただけるとうれしいです。
ご一緒してくださりありがとうございました。
講師のにしけんさん、青のたすきの理恵さん、弄月庵さん、みなさんと一緒だからできたことです。ありがとうございました。