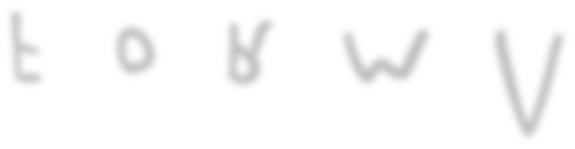-2025.11.15-
柿酢づくりワークショップ
11月8日ミライマオープンデーに、柿酢づくりのワークショップをしました。
参加者5名、みんな初めての柿酢づくりです。
今年の里山はどこも柿が鈴なり。ミライマには甘柿の木が2本、渋柿の木が1本ありますが、こちらも同じく鈴なり状態です。自然の豊かな実りをお裾分けしながらありがたくいただいていますがあまりにもたくさんの柿。もう少し何か利用できないものかと思っていたところ、柿酢づくりしましょう!という男子の登場で実現した今回のワークショップです。

まずは、ミライマの果樹の畑にある甘柿の収穫するところからです。なるべく熟したものがいいらしいです。鈴なりなので、カゴいっぱいになるのはあっという間です。
さて、今回は柿酢とコンブチャ(柿酢からの副産物)を作りましょうと言ってくれた長岡君が、作り方を教えてもらったというのでその方法で仕込みました。
①まずはさっと軽く洗う。皮に発酵に必要な酢酸がついているので洗いすぎないように。
②皮のまま柔らかそうなものは手で潰す。意外に潰れるものです。みんな握力強い。
③硬そうなものはカットして瓶に詰める。
④出来上がり。

※初心者の集まりに、今、まさに柿酢を仕込み中という助っ人登場で、一生懸命手で潰さなくてもカットしておいたらそれでOKときいて、なんだかみんなホッとしてました。
というわけで、レシピというほどのものでもなく、書いてしまえばなんだそれだけというシンプルさです。
なので、誰でもできるし1人でも簡単にできてしまいます。
が、、、
「どうするんといいんやろう?」とか、「どうなるんやろう?」とか、みんなでワイワイ言いながらとにかくやってみる手仕事の楽しさよ。
1人の『やったことないけど、ちょっとやってみたいんですよね。』という試みに、面白そう!と乗っかるワクワク。
そして、このあとに続くであろう、「こうなってきたよ〜」という完成までのプロセスの共有。

一緒に柿酢を仕込んだメンバーに、福知山に家族で移住され農業を始められた方がいらっしゃいました。彼女から『ローカルの豊かさを満喫♪』というメッセージが届きました。
まさしく、柿を収穫し柿酢を仕込むまで、全てがその場でサクッとできてしまうのはローカルならでは。
ずっと里山で暮らしていれば当たり前のことも、街で暮らしていれば当たり前ではないことがたくさんありそうです。

さて、
無事に柿酢はできますでしょうか。
【柿酢ができるメカニズムは?】柿(渋柿・甘柿どちらでも可)を酢に変える仕組みは、自然に存在する酵母と酢酸菌による二段階発酵で進みます。柿の糖分を「酵母」がアルコールに分解する「アルコール発酵」と、そのアルコールを「酢酸菌」がさらに酢酸に分解する「酢酸発酵」の2つのプロセスから成り立っています。これらの微生物が柿の糖分を栄養源として、時間をかけて発酵させることで柿酢が作られます。

1週間後、柿と水分が分離し酸っぱい匂いがそれとなくしてきました。それぞれの様子もLINEグループで共有中。経験済みの先輩からのアドバイスも入り順調です。
保存食作りや手仕事といったことをやってみると、各家庭の味がありそれぞれの方法があることも魅力の一つ、そして、こうしてみんなですることも喜びであり楽しみだと実感します。
「やってみたい」、「やりましょう」と声をかけてくれた長岡君ありがとうございました。そして、「面白そう」「やってみたい」と参加してくださったみなさんありがとうございました。